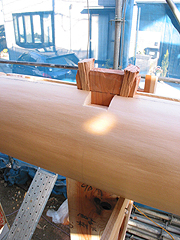合板類やボード類の使用は、家具や建具にいたるまで極力使用せず、また接着材も昔ながらのニカワを使用。
「拭き掃除をしたり、家を繕ったり、庭の草木の手入れをしたり、路地に水を打ったり、友人たちを呼んでお茶を楽しんだりと、暮らすことを趣味にしたい。」と願われての家づくり、土壁による住まうほどに深みをます昔ながらの家づくり(伝統構法)を目指します。
1.地鎮祭、木材伐採見学、基礎工事〜建て前
2.建て前〜棟上げ
3.土壁
4.完成にむけて-1
5.完成にむけて-2
6.完成写真
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||